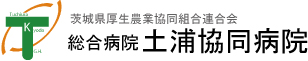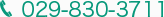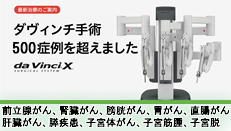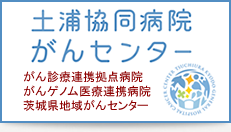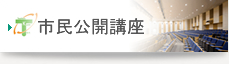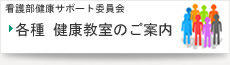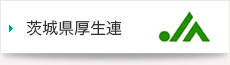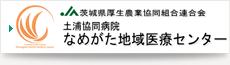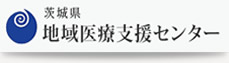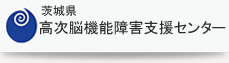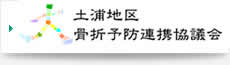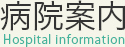 病院案内Hospital information
病院案内Hospital information
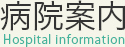 病院案内Hospital information
病院案内Hospital information
細菌検査
細菌検査とは
私達の体表、口、お腹の中や、生活環境のいたる所に、色々な細菌や真菌がいますが、提出された検査材料(喀痰、尿、便、血液、膿、分泌物、穿刺液etc…)から、病気の原因となっている菌(起因菌)を見つけて、その菌がどんな薬に効くのかを調べています。
検査方法
塗抹検査
検体をスライドガラスに塗り、染色して菌の有無や色、形、量などを顕微鏡で観察します。
培養・同定検査
培地(菌が好む栄養素を加えた寒天)に検体を塗り、適温で育てると、コロニーと呼ばれる塊を形成し、目で観察出来るようになります。菌の種類によって、色、形、生化学性状が異なるので、総合的に考え菌名を特定します。通常3~4日で結果がでますが、発育が遅い菌では1週間、真菌では1ヶ月間も培養を続けます。
薬剤感受性検査
検出された菌が、どの抗生物質に効くのかを調べます。菌ごとに決められた薬剤が塗布されているプレートに菌液を入れて培養し、菌の発育が阻止される最小の発育濃度を求めます。
遺伝子検査
結核菌の培養は時間がかかりますが、PCR法では、菌体内のDNAを特別な方法で増幅し、数時間で菌の有無が検査可能です。
ウイルス検査
下痢の原因となっているロタウイルスの検査。
毒素検査
病原性大腸菌(O-157など)が産生する毒素の検出や、抗生物質投与により腸内細菌叢が変化することによって起こる下痢の原因となる毒素の検出。
その他
- 定期的に職員(栄養科、保育士)の便培養の実施
- 必要に応じた環境調査・水質調査
- 菌検出状況や薬剤感受性状況などの情報提供
- 感染管理